2024/9/7
休んだつもりがかえって疲れた…。医学博士が教える、休みを効果的に変える4つのコツ
疲れ切って迎えた週末。ソファに1日中寝転がって、流れてくるショート動画を延々と見てしまう。気づいたらもう日曜日の夕方。心身ともにぐったりして月曜日を迎える—— 。
そんな一連の行動は、多くの人に身に覚えがあるのではないだろうか。
・効果的な休養には“DRIC”が必要
『あなたを疲れから救う休養学』(東洋経済新報社)を上梓した医学博士 片野秀樹さんによると、こうした行為は“休養”になっていないのはおろか、かえって疲れを増している可能性もあるという。
疲れているときこそ、効果的に休養を取りたいものだが、果たしてどのような休養が理想的なのだろうか。「効果的な休養に必要な要素が4つほど存在します。私はこれを『DRIC』と名付けました」(片野さん)
①ストレスと物理的・心理的に離れてみる
1つ目の「D」は、「Distance(距離)」を指す。
これは仕事などのストレスの原因から物理的、心理的に距離を取ることを意味している。「休養のためには、ストレスから離れることが大切。物理的に離れるのが一番ですが、それが出来ない時は目をつぶって楽しいことを想像して心理的に距離を取ることでも効果があります。
スマホの例で言えば、チャットやメールなどで仕事の連絡が来ることもあるでしょうから、そうした場合は物理的に距離を置くのがよいでしょう」(片野さん)
②スマホは時間を決めて触る
2つ目の「R」は、「Reset(リセット)」や「Refresh(リフレッシュ)」を表している。
自分が選んだ行動がリフレッシュになっていることが重要という意味合いだ。「スマホを見るという行為は、人によってはリフレッシュになるのかもしれません。そうした場合は、時間を決めて触るとよいでしょう。何時間もズルズルと触り続けるのは、休養としてはおすすめできません。リフレッシュのために、スマホと離れる時間を持てるとよいですね」(片野さん)
③自己投資の時間は休養になる
3つ目の「I」は、「Input(インプット)」や「Investment(投資)」を意味する。
片野さんいわく、アウトプットばかりを重ねることは休養にはならない。新しいことを学習したり、習い事の技術を上達させたりと、自己投資になるような行動は休養の一種なのだという。「スマホで動画やSNSなどを見る場合、それが自分を成長させるような内容のものであれば、休養につながります。しかし目的がなく、ただダラダラ見ている場合は、自己投資にはなりませんので、かえって逆効果になるでしょう」(片野さん)
④「自分のペースで歩く」のも、立派な休養
4つ目の「C」は「Control(コントロール)」を表している。
「自分が自分のペースで行動できているかどうか」というのがControlの肝だ。「自分のペースを乱されることは、実は人間にとっては大きなストレス。しかし日常生活を営んでいると、自然と社会のペースに飲み込まれてしまうことが多いもの。例えば仕事の帰り道に、周りを歩く人の歩調に合わせて早歩きしてしまっていることはありませんか?
本来であれば、自分の自由な時間のはずなのにいつの間にか社会に併せてしまっているのです。そうしたことに気づいて、自分のペースで歩いてみるということも、立派な休養になります」(片野さん)
本当はスマホを見たいわけではないのに、ショート動画やSNSをずっと見てしまうのも、もちろんストレスにつながるということだ。
その他にも、サードプレイスを持ち、1人で自分のペースで過ごす時間を持つことも有効だ。
家族がいる人は、休日の過ごし方を自分好みに設計して、家族とともに時間を過ごすというのも休養につながるという。「少し意識して休養の仕方を変えるだけで、心身ともに活力がチャージされ、元気に仕事や趣味、日常生活に打ち込めるようになります。
『DRIC』の他にも、具体的にどんな休養をすればよいか示した『7つの休養モデル』がありますので、組み合わせるとより効果的に休養ができますよ」(片野さん)
(参照)『休養学: あなたを疲れから救う』 単行本 – 2024/2/28 片野 秀樹 (著):1,617円









2024/9/6
医療で誘客に「待った」 成長戦略議論を巡り応酬 厚生部長「人手不足で厳しい」 知事「魅力づくりに協力を」
『くすりの富山』に代表される先進的な医療体制を生かし、誘客や関係人口の創出につなげようとする富山県成長戦略会議の議論に対し、有賀玲子厚生部長が医療分野の人手不足を挙げ「『来てください』と言える状況でない」と反論する場面があった。新田知事は「新しい魅力づくりのために協力してほしい」と求め、応酬を繰り広げた。
成長戦略会議では、有識者から「薬都・富山」の強みを生かし、ヘルスケアやアンチエイジングなど健康増進を前面に打ち出し、関係人口の呼び込みを図る提案があった。
有賀部長は、富大が医学科に特別枠を設けるなど、医療人材の確保に向けて努力していると指摘。「県民のため、地域のための体制を整備しようとあらゆる手段で人手を確保している中、外部からの受け入れはかなり厳しい。余剰がそもそもない」と主張した。
新田知事は「最先端の医療を提供するという話ではなく、例えば『大腸ポリープをばりばり取りましょう』ということだ」と説明したが、有賀部長は「まさに日常医療という話。内科が不足している富山県で、そこまでできるかということだ」と否定的な見解を示した。
2人の議論は平行線をたどり、田中地方創生局長が「県だけでできることと、国に対して言わないといけないこともあるかもしれない。精査する必要がある」と述べて場を収めた。
(金ひげ先生コメント)「医療ツーリズム」という言葉が大きなトレンドになっています。
自国より医療水準が優れている国へ行き、治療や健診などの医療を受けることを指し、がん治療や臓器移植などのほか、歯科医療・再生医療・美容整形・健康診断なども対象になっていますが、利用する人の多くは富裕層で、医療を受けるために長期的な滞在が見込まれることから、その間の観光産業や地域振興への恩恵も大きく、インバウンド市場として大きく注目されています。
「医療ツーリズム」における課題も明らかになっていて、例えば以下の問題が生じてきます:
①医療ツーリズムを受ける外国人が、より高額な保険外診療を求めた場合、医療機関の利益は増大し、経営の安定につながりますが、病院が利益を求めて医療ツーリズムの診療を優先すると、国内居住者の保険診療が後回しになりかねない(日本人の患者が受けられる医療の質が低下する可能性)
②医療ツーリズムを受け入れる場合、医療機関には多言語対応が求められ、文化的/食事背景の違いにも配慮する必要が出てくる。外国からの患者さんと意思疎通ができないと、治療や検査がスムーズに進められず、トラブルに発展する恐れがある
③そもそも日本の多くの地域は深刻な医師不足の状態にあり、医療ツーリズムの患者さんに対応するほど人的リソースを割けない。人的リソースが不十分なまま医療ツーリズムが拡大すると、それが先述①の保険診療の優先度の問題につながる可能性がでてくる
思うのですが、まずは③の医師不足の問題を解決しない限り、医療ツーリズムの受け入れは難しいのではないでしょうか? 問題を解決する1つの方法として、医療ツーリズムを専門に受け入れる病院を新設する(=通常の保険診療を行う病院とは区別する)方法があるように思いました。
何はともあれ現状、医療のレベルが高く、皆保険制度のある日本に住んでいると、よほどのことがない限り海外に医療を受けに行くことがありません。これは物凄く恵まれていることだと思います。

2024/9/5
猛暑の中“夏バテ対策”に食べられている食材1位は「豚肉」!
今年の夏も多くの都市で連日猛暑が続いています。気象庁の発表によると、2024年7月の東京の平均気温は28.7℃で、平年(1991年~2020年)よりも3.0℃高かったとされています。
夏の体調不良を指す「夏バテ」は、一般的に慢性疲労・食欲不振や消化機能の低下などが引き起こされた状態を指します。夏の高温・高湿度のほか、屋外と室内の寒暖差などにより体温調節を担う自律神経のバランスが乱れることが原因の1つと考えられており、日常生活の中で体調管理の話題に上がることも多い事柄です。
1.ユーザーアンケート回答者の約7割が「これまでに夏バテを感じたことがある」
2.もっとも行われている夏バテ対策は「水分補給」、「食事」「睡眠」関連も上位にランクイン
3. 夏バテ対策としてもっとも食べられている食材は「豚肉」
「夏バテに関する調査」詳細
1.ユーザーアンケート回答者の約7割が「これまでに夏バテを感じたことがある」
「これまでに『夏バテ』の症状を感じたことがありますか?」という質問に対して、68.6%が「はい」と回答しました。また、具体的な症状として「体がだるい」「疲れがとれない」「食欲不振」が上位に挙げられました。
2.もっとも行われている夏バテ対策は「水分補給」、「食事」「睡眠」関連も上位にランクイン
これまでに夏バテを感じたことがあると回答された方に、「夏バテ対策として行っていることがありますか?」と質問したところ、66.6%の方が「はい」と回答しました。具体的に夏バテ対策として取り組んでいることについては「水分を積極的にとる(57.8%)」のほか、「栄養バランスを意識した食事を食べる(39.2%)」「睡眠時間をしっかりとる(36.6%)」といった、食事や睡眠に関する内容が上位を占めました。
3. 夏バテ対策としてもっとも食べられている食材は「豚肉」
「夏バテ対策のために、積極的に食べている食材はありますか?」という質問に「はい」と回答した方へ具体的にどんな食材を食べているかを聞いたところ、第1位は「豚肉(38.7%)」でした。そのほか、TOP10には以下の食材がランクインしました。
第1位 :豚肉
第2位 :納豆
第3位 :梅干し
第4位 :酢
第5位 :うなぎ
第6位 :豆腐
第7位 :卵
第8位 :鶏肉
第9位 :レバー
第10位:枝豆
「夏バテ」は、「暑気あたり」「夏負け」などと同じく、夏の体調不良を指してよく使われる言葉です。今回のアンケート結果でも、暑さによって食欲が湧かない、疲れが取れないなど、「夏バテ」を経験したことがある方は多くいらっしゃいました。
具体的に、夏バテ対策として皆さまが食べている食材のランキングを見てみると、豚肉、納豆といった、エネルギーの代謝に必要なビタミンB群が摂れる手軽な食材が人気でした。うなぎはたんぱく質・脂質のほか、ビタミンA・ビタミンB群・ビタミンE・DHA・EPAなども含み、栄養価が高い食材です。夏の時期には、土用の丑の日にうなぎを食べるといった季節イベントとしても広く根付いています。
そのほか、梅干しや酢など酢っぱいものもランクインしています。レモンやすだちなどの柑橘類もそうですが、酸味があるものは食欲増進に役立ちます。また、唾液が出るので味を感じやすくして食べものを飲み込みやすくするほか、消化を助ける働きも期待できます。
夏の食事のよくある例として、そうめん・うどん・そばなどの麺類が増えたり、主食だけの食事になりがちです。食事内容が炭水化物に偏り、たんぱく質の摂取量が少ないと、エネルギー代謝に必要なビタミンB群などのビタミンやミネラルが不足してしまいます。1日3食、主食・主菜・副菜をそろえて食べるようにしましょう。
また、こまめな水分補給はもちろん、飲み物の温度も状況に応じて変えると良いでしょう。運動や屋外で活動してたくさん汗をかいたときは、冷たい飲み物が身体を冷やすことに役立ちます。冷房のきいた室内では、常温や温かい飲み物を選ぶと冷えすぎを防ぐことができます。

-1024x682.jpg)

2024/9/3-2
食べ物を選択する際の脳の働き 健康的な食生活を継続するには前頭前野が重要か? 同志社大学
人が「おいしいけれども健康によくない食べ物」に対して、「健康によいけれどもおいしくない食べ物」を選ぶときに、前頭前野が活動し、その活動は長期的な利益を最大にする自制心の強い人ほど大きくなることが報告された。群馬大学、同志社大学、自然科学研究機構生理学研究所、株式会社アラヤの共同研究の結果であり、「Cerebral Cortex」に論文が掲載されるとともにプレスリリースが発表された。研究者らは、「この知見は、人が健康を優先して食品の選択をする際、前頭前野の自制の機構が重要な役割を果たしていることを示唆している」と述べている。
食べ物を選ぶとき、おいしさや健康によいかは重要な視点。健康によい食事を摂ることは、自身の健康につながる。しかし、誰もがそのことを知っているにもかかわらず、おいしさを優先して健康に悪い食事を衝動的に選んでしまうことがよくある。例えば、脂肪分や糖分、炭水化物が不適切なほど多く含まれた食べ物が健康にはあまりよくないとわかっていながらも、つい手を伸ばしてしまう経験は誰にでもあるだろう。つまり、健康的な食べ物を優先して選択していくことは簡単ではない。
これは、おいしさより健康を重視して食べ物を選ぶためには、おいしさという目前の利益より、健康という長期的な利益を優先するための「自制」が必要だからといえる。それでは、健康を重視する食品選択を行う際に、人の脳はどのように機能しているのだろうか。そして、このときの脳活動は自制とどのようにかかわっているのだろうか。
・目の前の小さな利益と、長期的な大きな利益のどちらを選ぶか?
研究グループでは、おいしさと健康を指標にした食べ物を被験者が選択する状況で、脳活動を計測した。まず、被験者は食べ物を、おいしさと健康的かどうかで評価し、「おいしいけど健康によくない食品」、「健康にいいけどおいしくない食品」に分類した。そして、脳活動の計測中に、画面に表示されたこれらの2種類の食品のうち、どちらか食べたいほうを選択した。ここで、「おいしいけど健康によくない食品」ではなく、「健康によいけどおいしくない食品」を選んだ場合、おいしさより健康を重視したことに相当する。
加えて、将来得られる金銭報酬を選択する課題により、自制の強さを測定した。この課題では、獲得までの時間と金額が異なる2種類の報酬について、どちらかほしいほうを一つだけ選ぶ。例えば、「いますぐ5,000円をもらう」、または、「1年後に10,000円をもらう」かのどちらかを選ぶ。
ここで、「いますぐ5,000円をもらう」という選択は目前の利益を優先した結果であり、衝動的といえる。一方で、「1年後に10,000円をもらう」という選択は目前の利益よりも長期的な利益を優先しており、自制心が強いことを意味する。すなわち、獲得するまで待つ必要があるが、報酬の量が多いという選択をする人は、自制心が強いということになる。
食べ物の選択における脳活動を調べたところ、「健康によいけどおいしくない食品」を選んだとき、すなわち、おいしさより健康を重視する選択を行ったとき、前頭前野の大きな活動が観察された。さらに、金銭報酬における長期的な利益を優先する、つまり、自制心が強い人ほど、これらの領域の脳活動が大きいということがわかった。
一方で、自制心の強さは認知の機能と関係があるとこれまで考えられてきたが、認知の機能は、食べ物の選択における健康の優先とは関係がないことが示唆された。
・前頭前野における自制が健康的な食生活につながる
本研究の結果は、人がおいしさより健康を重視して食品を選ぶとき、長期的な利益を優先するという自制に関連した前頭前野の活動が重要な役割を果たしていることを示唆している。
この結果について研究グループは、「食べ物の選択は他の動物種にとっても大切な行動だが、健康を優先するという長期的な利益に基づく選択をすることは人に特徴的であると考えられ、人で最も発達している前頭前野が健康の優先に関与していることは興味深い。そして、健康的な食生活の継続には、この前頭前野における自制の機構が重要なのではないかと考えている」と述べている。
プレスリリース:健康を優先した食べ物の選択における脳機構を解明: おいしさの誘惑を乗り越える自制心(同志社大学)



(写真左から)飯坂温泉の夕飯に出た「うなぎ蒲焼」、恐山の宿坊で出た夕飯、マクロビ食。(photo by 金ひげ先生)
2024/9/3-1
【胃腸サポート】「胃の不調」、2人に1人に
腸トラブルに悩む人は多い。暴飲暴食、疲労、睡眠不足をはじめとした生活習慣の乱れに加え、日常生活における様々なストレスが原因とされる。新型コロナに対する不安は解消されつつある一方、物価上昇による生活への不安などが増す中、胃の不調を感じている男女が5割を超えるといった民間調査も。薬に依存しない日常的にケアできるサプリメントや健康食品の利用が広がっている。“胃の健康”分野では、健胃作用、胃粘膜の保護作用、抗ピロリ菌作用などを有する機能性素材が流通。機能性表示食品では、ヤクルト本社、明治が乳酸菌を機能性関与成分に「胃の負担を和らげる」飲料やヨーグルトを展開する。腸に関しては、腸内フローラのバランスを整えることの重要性が浸透。脳腸相関研究が進み、「第二の脳」としても注目されている。乳酸菌をはじめとした定番素材以外にも、各社によるエビデンスデータを兼ね備えた原料提案が活発だ。
胃は健康のバロメーター 様々なストレスが不調原因
何らかの胃腸のトラブルを抱える人は多く、「2022年国民生活基礎調査」によると、「胃のもたれ・むねやけ」の自覚症状がある有訴者率は人口千人あたり22.2で、女 性は男性(17.9)より高く26.2だった。昨年10月にマーケティング調査などを手掛けるヒューマン・データ・ラボラトリが男女2,000人を対象に実施した調査では、胃の不調を感じている人は55.9%で、前年調査から4.9ポイント増えた。20〜30代は6割を超えるなど、若年層は胃の不調を訴える割合が高く、特に20代女性は72.0%と最も高かった。胃の不調の原因は、「ストレス」(55.2%)、「食べ過ぎ」(48.0%)の回答が上位を占めた。予防対策では、「食べ過ぎない」「十分な睡眠をとる」「乳酸菌を摂る」「食物繊維を摂る」などの回答が挙がった。
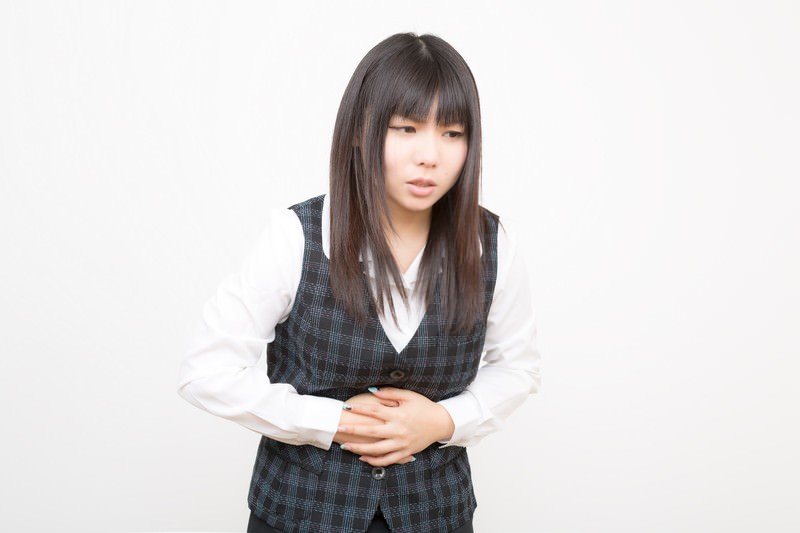


コメント