2024/7/13
「ゆっくりよく噛んで食べる」はなぜ良いのか? 咀嚼の重要性を裏付ける研究
早稲田大学 https://sndj-web.jp/news/002822.php
食事の初めに野菜を摂取する、いわゆる「ベジタブルファースト」の食事法は、食後血糖値の上昇を抑える働きがあることが報告されている。これは、野菜に多く含まれる食物繊維が関係していると考えられる。また、野菜の形状の違い(固形または液状)によって食後血糖値に及ぼす影響は異なることが報告されている。しかしながら、野菜を咀嚼して摂ることが食後血糖値とインスリンやインクレチンなどのホルモンの分泌に及ぼす影響は不明だった。本研究では、食前に固形の野菜を咀嚼して摂取することが食後の糖代謝に及ぼす影響について検証した。その結果、食前に固形の野菜を咀嚼して摂取することは、食後のインスリンおよびインクレチンの分泌を促進することが明らかになった。
※1 インスリン:糖を下げる働きをもつ膵臓のβ細胞で作られるホルモン。
※2 インクレチン:食事を摂ると腸管から分泌されるホルモンの総称で、インスリンの分泌を促進する働きがある。代表的なインクレチンとして、GIP(グルコース依存性インスリン分泌刺激ホルモン)とGLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)があり、前者は主に小腸上部のK細胞、後者は主に小腸下部のL細胞より分泌される。

2024/7/12
さまざまな食材の「混合食」は、栄養バランスが良いだけでなく地球環境にも優しい
東京大学が研究発表 https://sndj-web.jp/news/002818.php
東京大学の研究チームは、食生活の環境および健康への影響を探求し、混合食※1が栄養ニーズを満たしつつもカーボンフットプリント※2を低減させることを明らかにした。本研究では、料理ごとの価格と栄養価を考慮するとともに、カーボンフットプリントを評価した。その結果、牛肉を中心とした料理が最もカーボンフットプリントが高く、豚肉や野菜ベースの料理は低いことや、カーボンフットプリント全体に対して調理による直接的なCO2排出の影響は小さく、CO2の主な排出源は原材料の生産過程にあることが明らかになった。また、カーボンフットプリントの高い料理は高価であり、低いものは比較的安価であることもわかった。本研究は米国科学振興協会(AAAS)発行の「Science Advances」に論文が掲載されるとともに、同大学のサイトにプレスリリースが掲載されている。
※1 混合食:食材を肉、魚介、野菜などに分類するとき、単一の食材からなる料理ではなく、さまざまな食材を含む料理を指す。
※2 カーボンフットプリント:商品・サービスのライフサイクルの各過程で排出された「温室効果ガスの量」を追跡した結果、得られた全体の量をCO2量に換算して表示することをいう。
(金ひげ先生コメント)世界人口の増加や地球温暖化が進むにつれて、「温室効果ガス」の話題はいよいよ我々の身近な問題となっています。温室効果ガスの排出が少ない、「よりエコな」食スタイルが重要となっています。北欧の国々ではすでに、スーパーで販売している商品ごとに環境に対する負荷の程度がラベルされていたり、料理のレシピに温室効果ガスの排出量が記載されていたりします。我々日本人がまず取り組むべきは「フードロス」の問題でしょうか。ちなみに、年配の方よりも若い人たちのほうが環境に対する意識が高い、という調査結果があります。
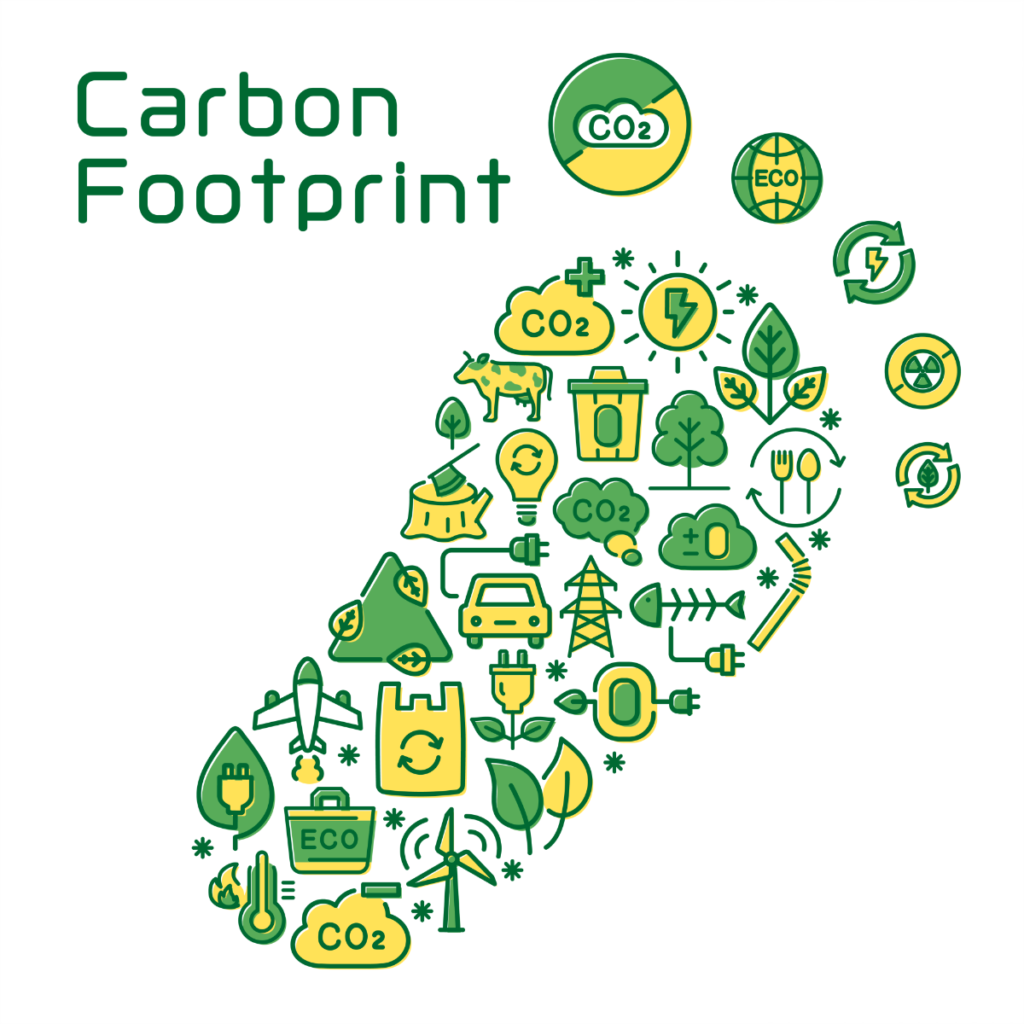
2024/7/10
食事を摂るシチュエーションによって栄養学的な質が変わる: 日本人111 人の生態学的瞬間評価
https://sndj-web.jp/news/002816.php
日本人成人の食事の種類(朝食、昼食、夕食)、同席者の有無、食事場所が、食事の栄養学的質と関連していることが明らかになった。
食事の栄養学的質が低いと、心血管疾患、がん、2型糖尿病などの疾患リスクが増加すると考えられている。誰とどんな状況で食べるかといった食事場面の特性は、食事の栄養学的質と関連する重要な要因である。例えば、外食は脂質や糖類が多い食事につながることが知られている。本研究の参加者は、30~76歳の日本人男女各111人。秤量法による食事記録を依頼し、4日間の飲食内容をすべて計量、記録してもらった。さらに、各食事場面の特性として、勤務日かどうか、食事の種類(朝食/昼食/夕食)、同伴者の有無、食事場所(自宅/外出先)、食事中のスクリーン使用(スマートフォンの操作やテレビ視聴)の有無を記録してもらった。男性においては朝食に比べて昼食の食事の質が低く、夕食の食事の質が高いことが明らかになった。また、男性は、一人で食べるときよりも誰かと一緒に食べるときのほうが食事の質が高いことが示された。女性に関しては、朝食に比べて夕食の食事の質が高く、自宅での食事よりも外食のほうが食事の質が高いことがわかった。勤務日かどうか、および、食事中のスクリーン使用の有無は、食事の質との間に有意な関連がみられなかった。個人の特性に関しては、男女ともに年齢が高いことと非喫煙者であることが、高い食事の質と関連することがわかった。さらに、女性ではBMIが高いほど食事の質が高いことがわかった。本研究は、成人における食事の栄養学的質と食事場面の特性との関連を、生態学的瞬間評価を用いて調べた初めての研究。この研究の結果は、食事の質を改善するための栄養教育や介入に貢献することが期待される。東京大学の研究グループが行った本研究
は「European Journal of Nutrition」に論文が掲載されるとともに、同大学のサイトにプレスリリースが掲載されている。

2024/7/9
母乳が腸内細菌叢を介して与える影響が、子の脳発達に重要と判明-東京農工大ほか
▼関連リンク・東京農工大学 プレスリリース
https://www.tuat.ac.jp/outline/disclosure/pressrelease/2024/20240612_01.html
東京農工大学は 母乳が腸内細菌叢形成を介し、脳発達に与える影響を解明したと発表した。この研究は、同大大学院農学研究院動物生命科学部門・永岡謙太郎教授らの研究グループによるもの。永岡教授らのグループはマウスを用いた実験により、母乳中のアミノ酸代謝酵素から産生される過酸化水素が乳仔の腸内細菌叢の形成に関与するだけでなく、腸内細菌叢由来の代謝物を介して脳の髄鞘発達に影響を与えていることを示した。本研究結果は、哺乳類に特徴的な母乳が仔の腸内細菌叢形成や脳発達を制御する仕組みの理解につながり、将来的には脳発達を促進する腸内細菌叢の形成が可能になると期待されます。研究成果は、「Gut Microbes」に掲載された。

2024/7/8
油脂を使ったレディトゥイート (RTE) 食品の多用が健康リスクを高める恐れを日本で初めて明らかに:家庭外で作られた食品や料理はその質と不足栄養素の補完が鍵となる
日本女子大学プレスリリース:https://www.jwu.ac.jp/unv/news/2024/cr5sr8000001su66-att/20240620_news.pdf
日本女子大学(東京都文京区、学長:篠原聡子)を中心とする研究グループは、油脂を使ったそのまま食べられる加工食品や調理済み食品、外食料理を多用する人では、栄養素の摂取バランスが偏り、脂質代謝に異常が生じ、がんや動脈硬化性疾患のリスクとなるトランス脂肪酸が血中に多いことを明らかにしました。総菜や弁当を買って食事を済ませたり、菓子を食事代わりにしたりする人が増えています。本研究により、便利さを優先して加工食品に依存した食生活は健康リスクが高いことを日本で初めて明らかにしました。



コメント