2024/8/5
健康マイレージ 小学生も対象に 湖西市、景品も増加
【静岡県】湖西市は、健康づくりに取り組んでポイントをためると抽選で景品が当たる「コーちゃん健康マイレージ」を実施している。本年度から子どもも参加でき、景品の種類も増やした。来年1月31日まで。参加対象は小学生以上の市民と市内に通勤、通学している人。健康づくりの目標を自由に設定し、達成すると1日1ポイントためられる。健康講座や献血など指定事業に参加すると、2ポイントもらえる。25ポイントを集めて応募すると「炭焼きレストランさわやか」の商品券5千円分や、健康支援品の詰め合わせなどが抽選で計約180人に当たる。市健康福祉センターなどで配っている紙のポイントカード=写真(左)=か、市公式ラインのショップカード機能を使って参加する。市の担当者は「自分に合った目標にチャレンジし、健康づくりのきっかけにして」と呼びかけている。
応募締め切りは来年2月6日。小学生には参加賞として、学習漫画「がんのひみつ」を贈る。
(金ひげ先生コメント)(私はやっていませんが)健康に良い行動をすることでポイントを獲得できて、たまったポイントを景品と引き換えできるサービスにすでに取り組まれている方、多いと思います。自治体や企業、健康保険組合が提供しているケースが多く、多くはウォーキング歩数でポイントが加算されるタイプです。上の記事で新たに開始されたサービスでは、健康講座や献血への参加もポイント加算される「複合型」のもので、なんとなく健康に対する意識を刺激されますね。景品が焼き肉屋(?)の商品券なのもユニーク。銭湯の入浴券や生ビール一杯サービス、なんてのもあると、良いですね😊

2024/8/4
キュウリの山 病封じ込めて 西条・世田薬師で祈願
キュウリに病魔を封じ込める伝統行事「きうり封じ」が7/24、西条市楠の世田薬師栴檀寺(せんだんじ)であり、参拝に訪れた約300人が健康や病気の回復を祈った。田中誠時住職(75)によると、きうり封じは江戸時代から300年以上続き、毎年土用の丑(うし)の日に合わせて開催。西日本を中心に行われ、病名や願いを書いた札をキュウリに貼り付けて祈願すると、身代わりなってくれるという。また、祈願当日は引き受けてくれた病が自分の身に戻らないよう、キュウリを食べずに感謝することが大切との言い伝えもある。当日、栴檀寺には県内外から6,000本ほどのキュウリが納められ、約70人の信徒が早朝から一本一本丁寧に札を貼り付けた。法要では、堂内に積み上げられたキュウリを前に田中住職らが読経し「えいっ」と力強く念を込め、祈願後は境内に運び出し、塚の中に投げ入れた。 新居浜市から家族で訪れた中萩小学校1年久門由佳さん(6)は「大好きなキュウリに、健康な日々を過ごせれるようお願いした」と笑顔。田中住職は「行事を通じてその年に流行している病などがよく分かる。お参りした人が心身ともに健康で幸せな生活を送ってもらえれるとうれしい」と話した。
(金ひげ先生コメント)「きゅうり」を主役にした神事は意外とあるみたいです。
有名なのは福島県須賀川の「きうり天王祭」で、約260年前に始まりました。参拝者は家から2本キュウリを「お仮屋」といわれる場所にお供えし、1本を持ち帰って食べると1年間病気に罹らないといわれています。また、岩手県諏訪町では「きうり天王宵宮」があります。
ちなみにキュウリは「最もカロリーが低い果実」として、なんとギネスに載っています!
水分が多くて栄養がない、というイメージを持たれていますが、キュウリはビタミン(特にビタミンKとC)と葉酸、銅やモリブデンといった普段なかなか取りにくいミネラルを含んでおり、特に夏は積極的に摂りたい食材です。

2024/8/3
「牛乳入りラーメン」を研究家が勧めるワケ
ラーメンに関連した研究では2019年、英国の栄養学専門誌「Nutrition Journal」に発表された「ラーメン店が多い都道府県では、脳卒中の死亡率が高い」という報告がある。自治医科大学医学部内科学講座神経内科学部門の松薗構佑講師らが行ったもので、4種類の外食店(ラーメン店、ファストフード店、フランスおよびイタリア料理店、うどんおよびそば店)の「店舗数」を都道府県ごとに算出し、「脳卒中」と「心筋梗塞」による死亡率を集計して外食店との関係を調べたところ、「ラーメン店の数」と「脳卒中の死亡率」に統計的に有意な関連性があったという。ラーメンが悪と決まったわけではなく、あくまで地域におけるラーメンの店舗数の比較である。松薗講師も、「ラーメンをたくさん食べると脳卒中で亡くなるという関係を直接示したわけではない」と前置きしたうえで、「けれどもラーメン店が数多くあるのは、そういう食事を好む方が多い地域であり、脳卒中の死亡率が高い傾向にあると考えてもいいと思います」と話す。脳卒中には、脳の血管に血栓が詰まる「脳梗塞」と、脳の血管が破れて起こる「脳出血」がある。死亡率が高いのは脳出血だ。さまざまな研究で「塩分」が血管にダメージを与えることがわかっている。「日本人の食事摂取基準」では食塩摂取量の目標値を成人1人1日あたり男性7・5グラム未満、女性6・5グラム未満に設定しているが、日本の伝統的な食事が高塩分であることもあり、日本人は世界的にみて食塩摂取量が高い。ラーメン一杯を完食すれば通常6グラム以上の塩分摂取だ。ラーメンを含む高塩分食ばかり摂取した結果、脳の血管がもろく(切れやすく)なってしまう可能性はあるだろう。しかもラーメンそのものも“糖質(麺)と脂質(スープ)の塊”である。外でラーメンを食べる場合はせめてスープを半分にして塩分を「取らない」か、「排出する」ほうに力を入れたい。野菜や果物に含まれるカリウムは、ナトリウム排泄の作用がある。今の時期ならバナナ、キウイ、スイカなどにはカリウムが豊富に含まれるので、食後に摂取してもいいだろう。そして一番のお勧めは、家で健康的なラーメンを作ることだ。管理栄養士でミルク料理研究家の小山浩子氏が「ミルクラーメン」を提案してくれた。文字通りラーメンに牛乳を入れるのだが、意外にもおいしい。小山氏によると「スープまで飲み干せるラーメン」なのだという。「日本人は塩分の3分の2を調味料から摂取しています。ですから調味料を減らせば簡単に減塩ができます。ところがそうなると、味が物足りなくなって続きませんよね。でも牛乳は、そのものが五味(甘み・酸味・塩味・苦み・旨み)をもっているので、味噌味・醤油味・塩味のいずれのラーメンでも調味料を半分に減らして牛乳を加えれば、味がなじんでおいしく減塩できるんです」インスタントのようなひとつの鍋で作るラーメンなら、ぎりぎり麺がつかるくらいの水分量でゆで、麺をゆで終えたら、半分以下の調味料を入れ、味をみながら牛乳を加える。「市販のラーメンに添付される調味料は塩分約3グラム、多いもので5グラムくらいです。できれば1・5〜2グラム以下に減らしたいところですね。また麺にもおよそ1・5グラムの塩分が含まれるので、手間はかかりますが麺を別ゆでし、ゆで汁を使用せずにスープと合わせれば、減塩効果が高まります。そしてスープは少なめに作ったほうが、牛乳を足すことで味を濃く感じるでしょう。七味唐辛子や黒胡椒などの香辛料で味を補ってもいいですね」(小山氏)ミルクラーメンの利点はまだある。
「牛乳には野菜や果物なみにカリウムが含まれるので、摂りすぎた塩分を体外に排出してくれます。また牛乳に含まれるビタミンB1は糖質(麺)の代謝を、ビタミンB2は脂質(スープ)の代謝を促します。ラーメンのスープはあまり良質な脂質ではありませんが、牛乳には抗酸化作用があるビタミンAも多いので、スープの悪影響をブロックする作用も期待できます」(同)小山氏は以前、出張先の青森県で「味噌カレー牛乳ラーメン」を目にした。しかしこれは隠し味に山盛りの塩を、最後に麺の上にバターをのせるのだという。店主に作り方を聞き、小山氏がその場で塩分計算をしたところ、1杯10グラムという試算だった。これでは意味がない。当たり前だが牛乳を足す分、調味料を引かなくては減塩などの健康効果を得られないのだ。ちなみに青森県は松薗講師らの研究で、人口あたりのラーメン店舗数が多く、脳卒中の死亡率が高い都道府県の1位(男性)と3位(女性)にランクイン。全国的に脳卒中の死亡率が高い地域だ。「最後にバターではなく、オメガ3を含む亜麻仁油やエゴマ油を数滴たらせば健康的で、むしろ脳卒中予防になるラーメンです」と小山氏。魚の脂肪に多く含まれる「オメガ3」と呼ばれる脂肪酸は、血液の凝固を抑え、脳の働きを良くしたり、中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールを下げる働きがあるといわれる。しかしオメガ3は熱に弱いため、小山氏が提案するように最後に“たらす”といい。また気をつけたいのは健康志向の人が選びがちな「ノンフライ麺」。「カロリーは抑えているものの、フライ麺と比較すると塩分が1グラムほど高い」(小山氏)という。フライ麺はカロリー高めが難点だが、私なら塩分が低いほうを選ぶ。食物繊維が豊富なメンマ、ワカメ、コーンなどをのせて具から食べるようにすれば、太る元凶である血糖値の急上昇を抑えられる。それでも高カロリー摂取が心配なときは、食後に軽く歩くといいだろう(30分でごはん半杯程度のカロリーを消費できる)。 同様に「ヘルシーカップ麺」にも注意したい。食べすぎは体に負担になると、健康検定協会理事長で管理栄養士の望月理恵子氏が話す。「低糖質がウリのヘルシーカップ麺はサイリウムや難消化性デキストリンといった、体内で食物繊維のような働きをする物質が入っていますので、ほかの栄養素の吸収をさまたげてしまう恐れがあります。プロテインを強化したラーメンも、一食あたりのタンパク質量としては不足しています。ヘルシーだからいくら食べてもいい、これだけ食べていれば安心と思っていると、栄養素の過不足が起きてしまうのです」何かに頼るのではなく、自分の体に合わせた方法で、おいしくラーメンをいただきたい。
(金ひげ先生コメント)ラーメン、私の身近でも好きな方本当に多いです。それぞれにこだわり的なものがあって、話を聞くと普段物静かな人も急に饒舌になったりして面白いですよね。
私はキライではないのですが、「酒のツマミにならない」という理由だけで、あまり食べません。
そりゃ、若いころは飲んだ後、豚骨ラーメン食べたりしていましたが。
脂肪と糖質、塩分が多い・・等々、ラーメンについては「健康に良い」ことに言及する記事や論文を見たことがありません。そんなに身体に悪い?? そのうちタバコみたいに税金かけられたりして・・・暴動起きるかもしれませんね怖。きっと。

・初めて食べました・・・「大ラーメン 全部マシ」後悔。ひたすらに。(photo by 金ひげ先生)
2024/8/2
日立システムズなど4社、PHR実証で有用性確認
日本ウェルビーイングコンソーシアムは、福岡県飯塚市で実施したパーソナルヘルスレコード(PHR)*サービスの実証事業で、健康無関心層の健康意識向上などの有用性が確認できたと発表した。今後、スマートフォンアプリを用いた健康行動と実証実験の結果をモデル化し、自治体や健康経営を推進する企業に展開する。本コンソーシアムは日立システムズ、沢井製薬、ANAホールディングス(HD)傘下のANA X、インテグリティ・ヘルスケアが昨年7月に立ち上げた。
日々の移動でマイルが貯まるANA Xの「ANA Pocket」と、沢井のPHRアプリ「SaluDi」を活用し、飯塚市で地域回遊や地域経済の活用による健康増進を目指す実証実験を行っていた。飯塚市民と地元企業の190人を対象に、4カ月間の徒歩移動や市内商業施設への訪問に応じたインセンティブ付与による活動量の増加促進と、PHRサービスに触れる環境を提供し健康行動を促した。実証実験の結果、72・8%が「実証前と比べて健康に関して意識することが増えた」と回答し、健康意識や運動習慣などに関して点数化した主観バランスの変化において、とくに健康無関心層の数値の改善がみられた。参加者全体の平均体重は0・6キログラム減、BMIは0・3減だった。健康無関心層は平均体重1・6キログラム減、BMI0・6減と有意な体重減少が確認された。
*パーソナルヘルスレコード(PHR):個人の健康・医療・介護に関する情報のことを指す。
自分の健康に関するこれらの情報を一人ひとりが生涯にわたって時系列的に管理・活用することによって、自己の健康状態に合った優良なサービスの提供を受けることができることを目指している。
(金ひげ先生コメント)わたしたちが心身の不調で医療機関にかかった場合、その時の診療の記録や検査結果などは、診療を受けた医療機関だけにカルテ(診療記録)として保存・保管されます。
処方されたお薬の情報や別の医療機関を利用した場合も、それぞれの病院にバラバラに保存・保管されていることが障壁になり、次に何か病気になったりした場合に以前の情報が十分に生かされてません。これは、多くの人に気づかれていませんが、非常にもったいない(無駄が多い)状況です。
例えば、大きな病院で入院や手術をすると、ものすごく多くの検査が施されますよね。でも、この病院でせっかく集めた「自身の検査データ」は、次に近所の耳鼻科やクリニックに行った際には当然共有されておらず、同じ検査を1からやり直すことになります。この状態は患者さんの体力や時間を奪うのみでなく、医療費が余計にかかることになります(特に検査費用は病院で支払うお金の中でも割合が大きいことをご存じだと思います)。
また、PHRが進むことで、命にかかわるけがや病気になった際でも自分の幼少期における既往歴や現在のアレルギー情報などが網羅された情報を確認することが可能なので、迅速かつ適切な医療を施すことが可能となります。この辺私は詳しいのですが、米国ではすでに、(匿名化した=誰のデータか判らなくした)PHRを医療機関や研究者、企業が利用できる状況となっており、新しい医療を創出するための大きな基盤になっています。日本政府も他国に立ち遅れないよう、さまざまな施策を行いはじめていますが、一般の方も、かかるお医者さんの技量がすべてを決めるこれまでの医療に対し、課題意識を持つべきなのではないか、と思う次第です。
・PHRについてもっと詳しく知りたい方、厚生労働省が作成した資料があるのでご覧ください↓
厚生労働省PHR資料:我が国のPHRの在り方に関する 基本的な方向性(案) (mhlw.go.jp)
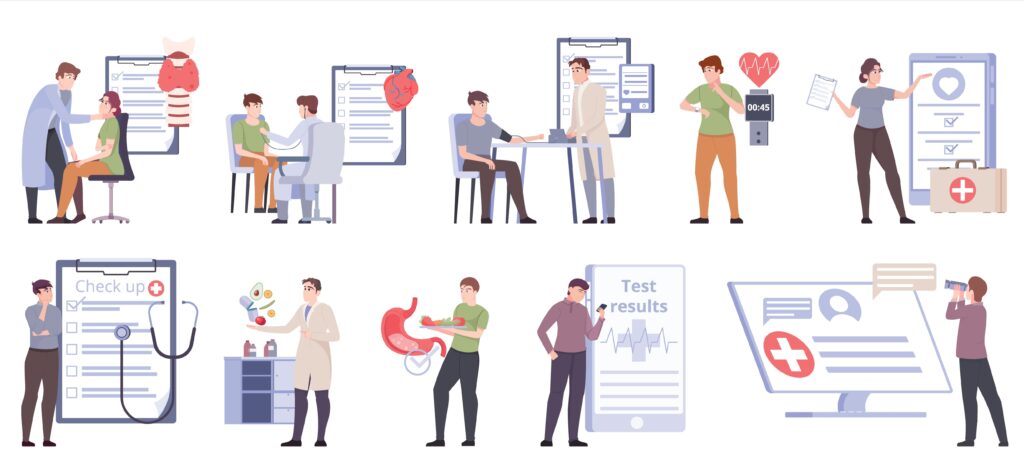
2024/8/1
宇宙で人体はどうなる? 筋線維の変化・ストレス・放射線・・・
宇宙空間での人体の生理的変化やその対応策を研究対象にする「宇宙医学」についての授業が、長岡京市下海印寺の高校であった。NASAやJAXAで研究した経験がある京都大の寺田昌弘准教授が教壇に立ち、生物や物理を学ぶ高校生が、教科や学問分野の垣根を越えた学際的な学びと研究の一端に触れた。寺田准教授は筋線維の変化、筋力や骨密度の低下、循環器系への影響、ストレスなど、宇宙で過ごすことによる人体への影響や感染症対策について解説した。生まれてすぐのニワトリの卵は無重力の宇宙ではかえらないといった実験などについても説明した。地球上とは異なる環境での宇宙医学の意義を語りつつ、「検証の機会が少ないのが課題。数年単位で宇宙に住めるのかといった問いへの答えは今の宇宙医学では出せない」と語った。また宇宙で生活する上での課題の一つに宇宙放射線を挙げた。放射線耐性のあるクマムシの遺伝子をもとにヒトの遺伝子をゲノム編集技術で改変すれば、放射線耐性を持つことができるのは「技術的には可能といえる」とした。一方、「遺伝子改変したヒトの子がどうなるかなど分かっていない。本当にやっていいのかという議論が必要」と強調し、人類が自らを含む生命の設計図を書き換えることの倫理的問題など、多角的観点から物事を考える重要性を説いた。
(金ひげ先生コメント)ヒトの遺伝子操作に関する話題が上がる時、常に語られるのが倫理の問題です。何年か前、中国の学者が遺伝子編集(遺伝子操作技術の一つ)を行った双子の赤ちゃんを作成した話題がありました。この赤ちゃんは遺伝子に特別な操作を行うことで、エイズウィルスが感染する際に必要なCCR5というタンパクを持っていません。ただし、CCR5は生体において免疫に関与すると言われており、果たしてCCR5が完全に無いヒトが天寿を全うできるのか、だれにもわかりません。万一、この子供たちが不幸な人生を送ることになった場合にこの研究者は責任を取れるのか(いや、取れるはずがない)、大きな議論を巻き起こしました。遺伝子操作は食糧生産や医薬品製造、エネルギー生産等で非常に大きな可能性を持っていますが、常に倫理面と併せて考える必要があります。
2024/7/31
腱を太く強化_マウスで実験/東京医科歯科大・浅原教授らチーム/人体への応用目指し 健康増進や能力向上に
ジャンプやダッシュといった瞬発力は、骨と筋肉をつなぐ腱(けん)が担っていることが明らかにされつつある。薬や注射によって腱を太くしなやかで切れにくくすることができれば、高齢者の健康増進や運動選手の能力向上に役立つ-。浅原弘嗣・東京医科歯科大教授や中道亮・岡山大病院研究准教授らのチームは、生まれた後にハツカネズミ(マウス)の腱をパワーアップすることに成功、人体への応用を目指している。 「将来、食べると身体がゴムのようになる『ゴムゴムの実』みたいな薬ができるかもしれません」と浅原教授。漫画「ワンピース」に登場する架空の果実のように、人間の腱を改造できるようになる可能性があるという。腱は繊維状のタンパク質(コラーゲン)が束になっているもので、筋肉と骨をつないで伸縮する役割がある。骨同士をつなぐ靱帯(じんたい)と似ており、傷つくと再生しにくい。浅原さんたちは約20年前、人やマウスの体内にあるさまざまな遺伝子を起動するスイッチである「転写因子」を調査し、マウスの全身におよそ1500あるスイッチがどこの部位、臓器に関係しているかを明らかにした。腱や靱帯に深く関わるスイッチである「MKX」も発見したが、スイッチがどうやって押されるのかは分かっていなかったが、外から加わる力に反応して細胞内にカルシウムを取り込む「チャネル」と呼ばれる部分にあることを探り当てた。遺伝的に機能が亢進したチャンネルがあると、細胞内にカルシウムを多く取り込むことが可能になる。それによって細胞は強く刺激され、スイッチが押されているのを見つけた。生まれる前の段階で遺伝子を操作し機能を亢進させたチャンネルを持つマウスを作成し、幅跳びをさせたところ、40~50センチの大ジャンプに成功した。普通のマウスと比べると5割前後高くジャンプできるようになった。その後の実験で能力アップに筋肉は関係せず、腱によるものだと確かめた(機能亢進しているマウスの腱は通常に比べ1.2倍程度太くなる)。生まれた後のマウスに遺伝子を組み込むことで、長く跳べるようにすることにも成功した。この仕組みは人間にも共通しているようだ。カリブ海の島国ジャマイカで、国際大会の出場経験がある陸上選手と一般市民の遺伝子を調査。カルシウムを多く取り込める変異を持つのは陸上選手で約54%と、一般市民の約32%を大きく上回った。高い能力を持つアスリートが、太くしなやかな腱を持っていることを裏付ける結果だ。iPS細胞を利用して移植用の腱を作ったり、体内のスイッチを刺激する薬を用いたりするなどの方法が考えられる。腱に近い組織が損傷する椎間板や、歯を支える歯根膜の治療への応用も期待できるという。浅原さんは「筋肉を肥大させるドーピングとは違って腱がしなやかになるよう誘導するので、健康や運動機能を増進できます」と期待する。
(金ひげ先生コメント)次の記事と併せて、SFの世界がいよいよ身近になってきました笑。
クマムシの耐放射線能と通常の人間をはるかに上回る運動能力を併せ持つ遺伝子組換え人間・・・・他に導入するとすればどんな生物の能力でしょうか?? 「ヒグマの筋力」、「猛禽類の視力」、「ニシオンデンザメの寿命(400歳の個体が最近見つかっています)」、もし、全部もっていたら??
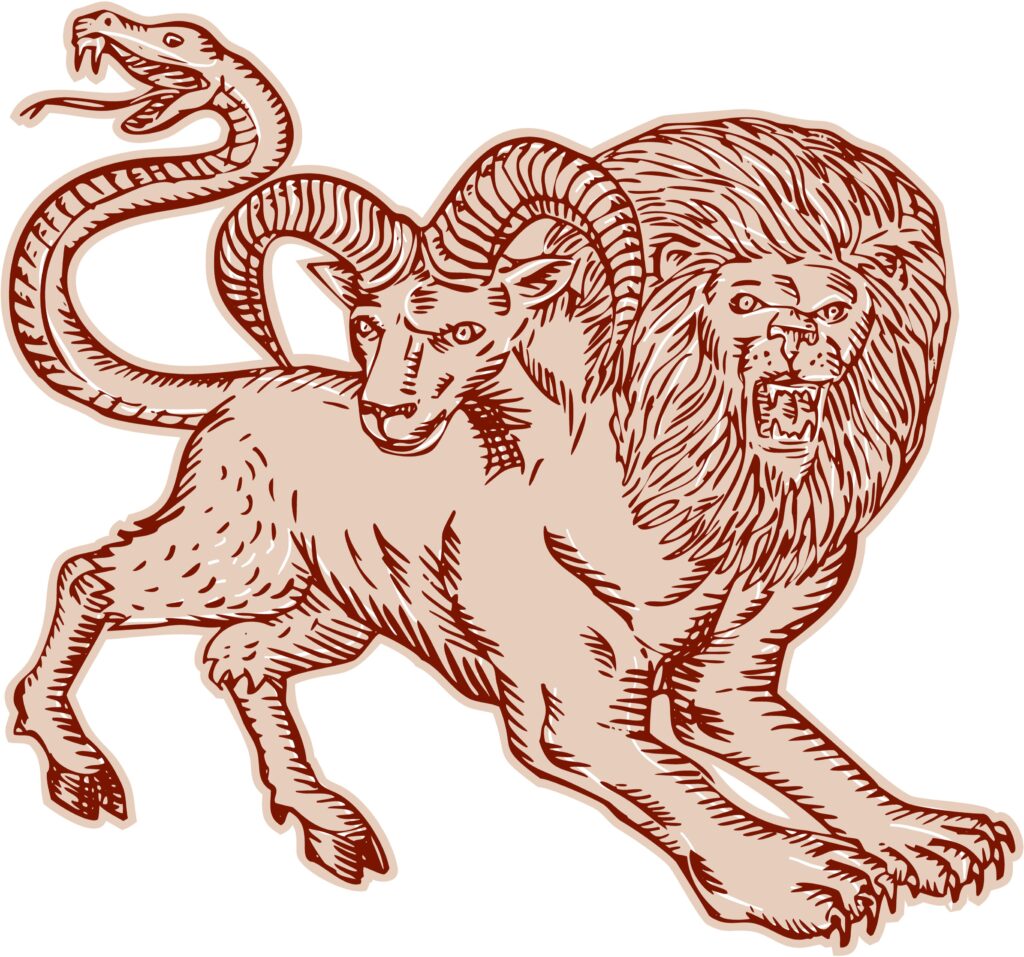
キマイラ:ギリシア神話に登場する怪物。ライオンの頭・ヤギの胴体・蛇の尻尾をもつ。
主に淫欲や悪魔を表す存在で、ライオンの頭の部分は「恋愛における相手への強い衝動」、ヤギの胴の部分は「速やかな恋愛の成就」、蛇の尾は「失望と悔恨」を表すとも言われている。
生物学で用いられる「キメラ」の語源となった。生物学でいう「キメラ」は、同一の生体内に異なる遺伝情報を有する細胞が共存する。「ヒトキメラマウス」→身体の一部にヒトの細胞を有するマウス。ヒトを模した動物として研究に用いられる。


コメント