2024/8/24-3
元箱根駅伝ランナーに聞く、ランニング1年目に知っておきたかった9つのこと
ランニングは、健康維持だけでなく心身のリフレッシュや自己挑戦の手段としても人気を集めている。しかし、始めたばかりのランナーには多くの壁が立ちはだかるものだ。今回は元箱根駅伝ランナーであり、Runtrip代表も務める大森英一郎氏に、ランニング1年目に知っておきたかった9つのことを聞いた。
1. 自分に見合ったハードルから始める
ランニングを始める際にまず知ってほしいのは、「ランニング=苦しいことではない」ということだと大森氏は語る。「何キロ走らなければいけないとか、何分で走らなければいけないとか、ランニングを楽しむという観点から言えば、そういったことは気にしなくていい。もっとハードルを下げて良くて、むしろいかに苦しまずに走れるかが大事なんです」
2. 走らない日をしっかりと楽しむ
ハードルを下げる具体例として、大森氏は「あえて走らない日を設定する」ことをあげている。「ランニングは三日坊主でもいいですし、一日坊主だっていい。ランニングを続ける上では、走らなくてもいい日を意図的につくってあげることも重要なポイントになってきます」。走らないと決めた日には、その1日を楽しむことも大切だという。「ランニングが習慣化してくると何もしないことに罪悪感を感じてしまいますが、リフレッシュの意味も兼ねてしっかりと楽しんで過ごしてほしいですね」
3. カタチから入っていい
新しいランニングシューズやウェアを揃えることで、モチベーションが上がることもある。「自分の気分が上がるギアやシューズを揃えた方が、外に出たくなるもの。初心者だからといって臆することなく、カタチから入ってもいいんです」
4. カタチから入らなくてもいい
その一方で、「もちろんカタチから入らなくてもいい」と大森氏は続ける。「安全に走ることを考えると適切なギアはありますが、スニーカーでも走れないわけではありません。特別なウェアがなくたって走ることはできますし、それくらいランニングは自由なもの。カタチに縛られて走れないくらいなら、カタチから入らなくてもいいんです」
5. 知らない道を走るのは楽しい
大森氏は「旅先や出張先で、知らない街や道を30分走るだけでも新鮮な体験ができる」と語り、またそういった体験は、特別な場所でなくても味わえるのだと説明する。「例えば自分の家の周りでも、意外と駅や目的地との最短距離しか知らなかったりしますよね。絶景のロケーションでなくても、普段行ったことのない場所や道に入ってみるだけで、いつもと違った楽しいランニング体験になるんです」
6. 数字を無視していい
タイムや距離、ペースに心拍数など、ランニングというスポーツはあらゆる数字で評価される。だからこそ、数字はあくまでも指標の一つとして捉え、ときには数字を気にせずに楽しんでほしいと大森氏はアドバイスする。「自分が気持ちいいと思えるペースで走れば、それだけで立派なランニング。歩いてもいいし、何キロ走らなければいけないということもありません」
7. 数値目標を定めてもいい
では、タイムを気にしたり、記録を更新することを目標にしてはいけないのかといえば、そうでもない。大森氏自身も「数字に注目することで自分が成長している過程が分かり、それもまた良い経験になった」と語っている。数字だけに縛られるとどこかで疲れを感じ、反対に、数字に縛られないと張り合いがなくなってくる。どちらもランニングを楽しむ上での重要な選択肢であり、重要なのは今の自分がどちらを楽しいと感じるかを見極めることだと大森氏は述べている。
8. ランニング仲間ができる
ランニングを通じて交友関係が広がることも大きな魅力の一つだ。「いつもランニングしている時に出会う、名前も仕事も知らないけれど友人と呼べる関係の人たちが私には沢山いて、大人になってから友達が増えました」と大森氏は語る。
9. 続けることで人生が変わる
交友関係の広がりからも分かるように、ランニングを続けることで変化するのはフィジカルだけではない。「私の場合、痩せたり、体脂肪率が何パーセントになったりといった健康面での改善以上に、メンタル面での改善が顕著にありました。また、それによってもたらされるポジティブなサイクルを実感することも多く、ランニングを始めてから人生が変わったと大袈裟でなく感じています。
だからこそ、苦手意識や苦しいイメージを持つ人々に、もっと自由にランニングを楽しんでもらえるようになってほしいですね」 そう大森氏はまとめる。第一歩を踏み出すきっかけとして、これらの9つのアドバイスを参考にしてみてもらいたい。
(金ひげ先生コメント)私もランナーです。もう10年くらい続けています。
ほぼ毎朝、出勤前に30分-1時間程度走っていますが、私が一番実感するのは、走っている間にアタマの中が整理される、ということです。無心に走っているときは、あまり何も考えていないことが多くて、もしかすると『マインドフルネス』に近い状態なんじゃないか、と感じています。この記事の9.に該当するでしょうか。『8. ランニング仲間ができる』は、自分には”ソロランナー”の自分には残念ながらなかったですね苦笑。ほかのランナーを見ても、顔見知りになって仲良くしている姿を見たことがあまりないですね・・・。

2024/8/24-2
健康食品―摂取量・体調記録を 専門家に聞く被害予防の注意点 薬との飲み合わせ、医師や薬剤師に相談
小林製薬(大阪市)の「紅こうじ」サプリメントを巡る健康被害問題を受け、ドラッグストアや通信販売で手軽に購入できる「健康食品」との付き合い方に関心が高まっている。基本的な注意点などを専門家に聞いた。
「大前提として全ての人に完全に安全な食品というものはない」と指摘するのは、東京都食品安全情報評価委員会委員で、静岡県立大の梅垣敬三客員教授(食品安全学)。例えば、アレルギー症状を引き起こす恐れがあるピーナツなどがよく知られている。
食品の場合、人体に影響がある「有害物質」は含まれていたとしても極めて微量なため問題はない。だが、栄養素を効率よく取るため食品内の成分を濃縮したサプリなどの健康食品は「有害物質も多く取り込むリスクが高まる」という。
梅垣客員教授が提案するのが「摂取メモ」をつけることだ。口にしたサプリの種類と量を手帳などに記録し、体調を○、△、×の3段階で自己評価する。「×が続けば摂取を直ちにやめて医療機関に相談する。自分で把握することが被害拡大の予防になります」
薬との飲み合わせが不安だったら、どのようにしたらいいのだろうか。日本臨床栄養協会(東京)の千葉一敏事務局長は「医薬品を使っていたり、病院で治療を受けたりしている場合は、医師や薬剤師に必ず相談すること」と強調する。商品パッケージの裏面に「医薬品を服用中の方は医師、薬剤師に相談の上、お召し上がりください」といった注意事項が書かれていることも少なくない。
さらに、求めている成分や量がきちんと入っているかどうかを確認する。「1日に○粒で○ミリグラム」といった具体的な情報が書かれているかどうかがポイントになる。
そもそも健康食品は病気の治療を目的としているものではない、と千葉事務局長。「高血圧症なのに『(血圧への効果がある)特定保健用食品の飲料を飲んでいるから』と、病院に行かないケースがあるが、それは間違っている。(利用の仕方が)分からなければ、専門家に聞いてほしい」
厚生労働省のサイトでは「いわゆる『健康食品』」に関するページの「アドバイザリースタッフ」の項に、相談可能な団体(日本食品安全協会、アドバイザリースタッフ研究会など)のURLを掲載している。
また、日本臨床栄養協会は、保健機能食品やサプリメントの知識を習得する「NR・サプリメントアドバイザー」認定試験を実施。協会サイトの「お問い合わせフォーム」で消費者の一般的な質問に対応している。
(金ひげ先生コメント)最近、がんに罹患したある芸能人がご自身のブログで、医師から診断を受けた後、ものすごくショックで、インターネットで治療法を探しまわった、と言っていました。情報として出てくる中に怪しい健康食品や宗教がたくさんあった、ということです。自身が「がん」であると診断されると、精神面がかなり弱くなるため、健康な時は絶対に見向きもしない治療に思わず引き寄せられそうになると発言していました。この記事にあるように、がんや高血圧を含む病気になったときは、まず医師の診察を受けて、しかるべき医療(投薬など)を受けるのが前提となります。そのうえで、医療だけでは満たされない部分を、本ブログで扱う様々な「補完代替療法(マッサージや鍼灸、漢方等を含む)」によってまさに『補完』し、治癒に向けたより良い生活を送ることが大事だと考えます。補完代替療法を利用する際は、今飲んでいる薬との組み合わせが非常に重要で、組み合わせ方が悪いと逆に回復を遅くしたり、薬の副作用を増強する場合があります。必ず、専門家に相談してから利用しましょう!

2024/8/24
マイナ保険証 「薬局で使う」7% 病院利用率のほぼ半分 処方箋の習慣 変わらず
国がマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」の利用拡大を図ろうと、薬局へも働きかけを強めている。ただ薬局では健康保険証の提示は必須でなく、病院などが発行する紙の処方箋で薬がもらえるため、利用率は伸び悩んでいる。
愛知県扶桑町の「はぐろ薬局」では、窓口にカード読み取り機を置きマイナ保険証が使えることをアピールする。「マイナ保険証はお持ちですか」。薬剤師が患者らに声掛けするが、利用率は5%ほど。訪れた60代の主婦はマイナ保険証は持っているが、「処方箋で薬をもらえるので、わざわざ出すのは手間」と話した。薬剤師の奥村智宏さん(51)は「習慣を変えるのは簡単ではない」と語る。
国は12月に現行の健康保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化する。厚生労働省によると、現在薬局で保険資格を確認する方法は、処方箋、現行の保険証、マイナ保険証の三つがあり、12月以降も紙の処方箋は残る。
厚労省の調査では、5月時点で薬局のマイナ保険証の利用率は7・40%。病院の利用率の14・83%を大きく下回る。担当者は「処方箋で済む薬局では保険証を提示する慣行がなかったためでは」とみる。
国は全体的に利用率を押し上げようと、1月からマイナ保険証の利用者数の増加に応じて施設に支援金を出している。支援金の上限は病院が最大20万円、診療所・薬局が10万円だったが、6月下旬に2倍に引き上げることを決めた。
全国でチェーン展開する大手薬局では5月、マイナ保険証しか使えないと誤解させるような対応が窓口であり、利用者に謝罪するトラブルもあった。広報担当者は「マイナ保険証のみの受け付けとは言っていないが、そう受け取らせる説明をしてしまった」と話す。
マイナ保険証を提示してもらうことのメリットはある。患者の同意を得て過去に処方された薬の情報をオンラインで薬剤師と共有することで、重複処方や悪影響のある薬の飲み合わせの防止につながる。
ただ、現状はリアルタイムで情報共有できる電子処方箋システムの導入率が1割台にとどまる。そのため、国は当面の間、薬の処方を記録する「お薬手帳」の持参も呼びかけている。名古屋市内の薬局を利用した60代の男性は「マイナ保険証でデジタル化を推進しながら、紙のお薬手帳を持ち歩けというのは矛盾している」と首をかしげた。
6月に日本薬剤師会会長に就任した岩月進・愛知県薬剤師会会長(68)は「マイナ保険証が普及すれば、重複処方が減り、医療費削減につながる。今は制度の過渡期でメリットを感じにくい面もあるが、利用者に丁寧に説明して理解を得ていくしかない」と話す。
(メモ)マイナ保険証 マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたもの。マイナカードを取得した上で、保険証をひも付ける作業が必要。国は12月2日以降に現行の保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化する。マイナカードを取得していない人やひも付けをしていない人には、現行の保険証の代わりに「資格確認書」を交付する。別の人の情報が誤って登録されるなど、ひも付けミスが約9200件以上起きている。
(金ひげ先生コメント)2016年に交付が開始されたマイナンバーカードの申請率は今や78.5%となっています。健康保険証としての利用登録率も74%に至り、着実に普及が進む一方で、さまざまな課題も明らかになっているようです。一点目は、住民票の誤発行や情報登録時のひもづけ誤りなどが発生したことで、今一つ信頼性に欠けること、もう一点は。健康保険証をマイナンバーカードへ一体化する「マイナ保険証」のベネフィットが、十分に実感されていないことです。厚生労働省が2023年5月に実施した実態調査によると、マイナ保険証への切り替えによって得られるベネフィットを認知している人は加入者の2~3割にとどまっています。通院などの受付の際の手続き簡素化や、自分自身の服薬の履歴をマイナポータルで閲覧できるといった現状の機能から得られる利便性の認知には限界があるため、「将来実現を目指す施策の具体化」と、「施策の実現によって得られる国民の利便性」を明確にすることが、賛同を得るためには求められています。

2024/8/23
出不精は大損! 健康に5000万円の価値があるワケ
心身が健康であれば、医療費や介護費用はかかりませんし、働ける期間が延びることで収入も増えるため、健康はある意味で資産といえます。では、健康にはどれだけの経済的価値があるのか、試算してみましょう。
40歳独身、35年ローンで4000万円のマンションを購入したばかりのAさんのケースを例に考えてみましょう。この時点での貯金額は500万円です。
まず、Aさんが日頃から食生活や体調管理に気を付け、70歳までスポーツジムで定期的に運動をしていた場合のパターン①から。
このケースのAさんは健康を維持できていたため、60歳で定年し、2000万円の退職一時金を得たあとも継続雇用で65歳まで働きました。65歳からは年金受給を機にリタイア。70歳以降は徐々に老化現象が出始めたため在宅の介護サービスを受け、加齢とともに要介護の区分は上がっていったものの、大病はなし。経済的負担はそこまで大きなものにはなりませんでした。
85歳で他界した際には850万円の預貯金が残り、生涯を通じてのトータルは黒字だったことになります。
次に、40代から高血圧症を抱えていたパターン②では、40代から通院していたものの、55歳で脳卒中を発症してしまいます。手術で一命はとりとめましたが、後遺症によって配置転換となったことで収入は減少。その後も順調に働けたとはいえず、57歳で早期退職を余儀なくされたことで退職一時金は1400万円にとどまりました。また、早期退職して収入がなくなったことから年金を60歳で繰り上げ受給したため支給額は24%減少。
現役時代から持病があったことや運動不足だったためか、55歳のときに発症した脳卒中に続き、75歳で脳血管性認知症を発症し、85歳で亡くなりました。脳血管性認知症は薬物療法や在宅介護の費用が高額になり、75歳から1000万円以上の支出を余儀なくされています。収入の低下と医療費が大きく響いたことで、他界した際の預貯金はマイナス4002万円と、大幅な赤字となってしまいました。
2つのケースでは、預貯金に5000万円近い差が生まれています。「健康の価値は5000万円」というのは言いすぎかもしれませんが、健康も立派な資産だということがわかります。ですが、健康の大切さはわかっていても、行動に移すのは難しいもの。
私がFPとして健康を重視したい人に選択肢のひとつとして提案するのが、保険会社各社が注力している「健康増進型保険」というジャンルの保険です。
健康増進型保険は、保険加入によって健康増進や生活習慣改善につなげられることをコンセプトにした保険のことで、おおまかに分けて
①「喫煙の有無や健康状態で保険料が割引される」
②「健康診断の結果で保険料が割引・還付金が受け取れる」
③「運動習慣など健康への活動で保険料が割引・還付金が受け取れる」
という3つのタイプがあります。
たとえば、SOMPOひまわり生命の「じぶんと家族のお守り」という保険は加入者が亡くなった場合や高度障害状態になった場合に年金が受け取れる収入保障保険ですが、「健康☆チャレンジ!制度」というプログラムが付帯しており、契約から2〜5年目に会社の定めるBMIや血圧などの健康状態をクリアすると、保険料の割引と、契約日にさかのぼって計算した保険料差額相当額が祝い金として受け取れます。
また、住友生命の「Vitality」は、同社の対象商品に付加するオプションのような制度です。年間で行ったウオーキングの歩数や健康診断の数値、生活習慣状況に応じて会員ステータスが決まり、翌年の保険料が増減するというもの。割引を毎年積み重ねていくと、最大で保険料は3割引きになります。
このVitalityの面白い点は、生活を改善できずに既定のポイントが貯められなかった場合、3年目からは保険料が2%ずつ上がっていく点です。
「健康を維持できないと、保険料が値上がりする」という点は大きなデメリットといえますが、自らの努力が保険料の割引やキャッシュバックという形で見える化される仕組みのため、行動心理学の観点から見てもモチベーションを維持し、努力を続けやすい仕組みだといえます。
目先のおトク感だけではなく、Vitality加入者は死亡率が非加入者より約43%低く、入院率も18%低いという数字が出ています。さらに、会員ステータスが最上位のゴールド会員は最下位のブルー会員より死亡率が約77%低く、入院率は50%低いというデータもあります。
「健康はお金で買えない」とはよく言ったものですが、健康に寄与する習慣や環境をお金で整えることはできるかもしれません。
(金ひげ先生コメント)終わりのほうに出てくる住友生命の生命保(Vitality)の仕組み、とても効果がありそうですね。Vilatityに加入した時点で保険料が15%割り引かれ、2年目からの保険料は健康増進への取り組み次第で決まるシステムです。ヒトは損をすることを恐れる動物なので、2年目からの保険料が上がらないよう一生懸命努力する、ことになるようです。
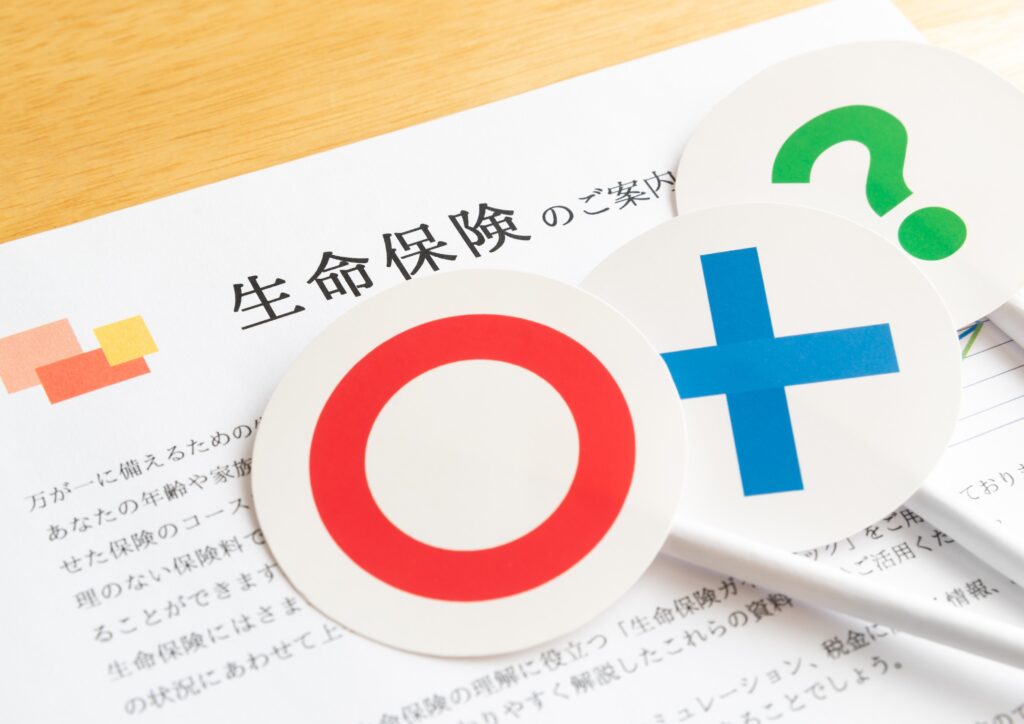
2024/8/21
超加工食品(UPF)は食べずにいられないように作られている…専門家が勧める、UPFを遠ざける3つの方法
*超加工食品(UPF):糖分、塩分、脂肪を多く含む加工済みの食品。スーパーやコンビニに良く置かれている。硬化油、添加糖、香味料、乳化剤、保存料などの添加物を付与して、工業的過程によって作られる、常温でも保存することができて日持ちする。超加工食品は食品添加物を多く含むうえ、さらにカロリー・塩分・糖分・脂肪分が多い。
ロンドン大学哲学研究所の所長であるバリー・スミス(Barry Smith)教授は、以前はケロッグ(Kellogg’s)やコカ・コーラ(Coca-Cola)、フェレロ(Ferrero)などと仕事をしており、その頃、超加工食品(UPF)は彼の食事の30%から40%を占めていたとBusiness Insiderに語っている。普通のキッチンにはない食材や製法で作られるUPFは、欧米の食生活には欠かせないものとなっている。
ノースイースタン大学ネットワーク・サイエンス研究所が2024年に取りまとめた研究論文(査読は済んでいない)によると、アメリカで供給されている食品のうち、UPFが73%を占めていることが明らかになった。スミスによると、嗜好性が極めて高いUPFは、脂肪と炭水化物の比率が完璧であるため、一旦食べ始めると、やめるのはほぼ不可能になってしまうという。「これらの食品は、我々の体のシステムが非常に欲しているものであり、実際に満腹になるメカニズムを遅らせている」とスミスは言う。
Nature Foodに掲載された2023年の研究では、食事に含まれる嗜好性の高い食品が多いほど、被験者の総摂取カロリーが高くなる傾向があることが明らかになった。スミスは2020年頃からUPFの摂取を減らし始めた。工業的な食品加工の害に光を当てたベストセラー『Ultra Processed People』の著者であるクリス・ヴァン・タレケン(Chris van Tulleken)博士からポッドキャストに出演するように頼まれたのがきっかけだった。「彼らが私から知りたがっていたのは、我々が消費し、求め、渇望するような食品を製造するために、どのような感覚的トリックやテクニックが使われているのかということだった」とスミスは述べている。
このことをきっかけに、スミスはUPFが健康に及ぼす影響をより意識するようになった。例えばThe BMJに2月付で掲載された研究論文によると、UPFは2型糖尿病、うつ病、心血管疾患など32の健康問題のリスク上昇と関連付けられている。そして彼はこのような懸念を仕事に反映させるようになった。「自分が知らず知らずのうちに、食品業界のこうした動きを手助けしてきたのではないかと考えるようになり、そんなことはできないと思うようになった」食品会社はUPFを抗えないほど魅力的にするために感覚・知覚学の科学者や化学者を雇っているが、彼らは自分たちが手助けして作られた製品を食べない傾向があるとスミスは言う。
「彼らはデザイン、フォーマット、工業的処理がどのようなものであるかを知っている。だからといって彼らがそれを自分で食べたいと思うとは限らない」スミスはもうUPFを製造する企業とは仕事をしていない(だがそもそも、人が食べずにはいられない食品の作り方をアドバイスしたことはないと述べた)。スミスは自身が食生活を変える際に役立った3つのことをシェアしてくれた。まずUPFから離れる(そうすると、もう戻りたくないと思うだろう)。UPFの健康リスクについて知れば知るほど、スミスはUPFを食べたくなくなったので、完全に断つことにした。
彼はUPFを摂取すると生理的な影響があることに気づいて嫌になり、時間が経つほどますます嫌いになった。「あまりにも刺激が強く、味が濃く、ある意味、主張しすぎていると感じるようになった」そして、気分が良くなってきていることに気が付いた。UPFが健康に及ぼす悪影響のことを考え、意識的に避けていたところ、その効果がとても望ましいものであることが分かったのだ。よりエネルギッシュになり、満腹感が長く続き、満腹感を感じたら食べるのをやめることができた。また、努力しなくても体重が減った。
彼は以前、UPFを実際に楽しんでいたというよりも、夢中になっていた。
だからこそ、UPFから離れたことで、そのありのままの姿を見ることができたと彼は考えている。「どうしても食べたいという欲求を断ち切ると、食べ過ぎることのないごく自然な摂取量に落ち着いていくことが分かるだろう。UPFは、我々が他の何よりも好きな食べ物というわけではないが、食べたくて仕方がない食べ物なのだ」スミスの場合はこれでうまくいったが、きっぱりやめるのは誰にでも向いているわけではない。
登録栄養士のリニア・パテル(Linia Patel)が、UPFを減らすことについて以前Business Insiderに語っていたように、新しい習慣を作るには行動を変える必要がある。自分に合ったものを試してみるといいだろう。 UPFの摂取を見直すことで、それを本当に楽しんでいたのか、ただ夢中になっていただけなのか、問い直すことができるようになる。
(金ひげ先生コメント)以前はさほど気にならなかったのに、最近急にコンビニのおにぎりが食べられなくなってきました。仕事が多忙な時期にお昼連続して「コンビニめし」を食べていたのですが、ごはんに混ぜ込んである油脂と調味料が妙に気になるようになってきたのです。おそらく、ご飯が冷えても固くならないよう、添加されているんだと思いますが、何か舌先に油分が残る感じがします。コンビニで売られている食べ物はとても良くできていて、それなりに美味しく食べられ便利ですが、「味+保存性」が一番に優先されて作られている気がします。添加物を加えない食品を冷凍で販売し、購入時に電子レンジで解凍・あたため するような商品がもう少しあってもいいかもしれないと思いました。



コメント